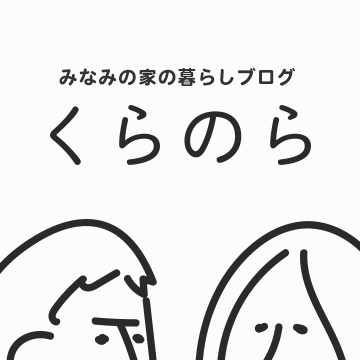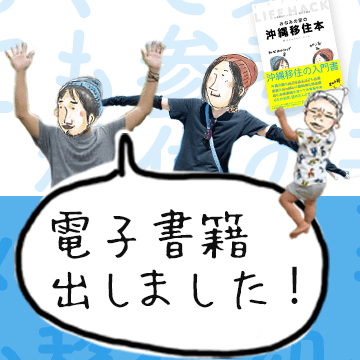ことわざでUXをザックリと向上させる
すっかり有名な言葉になりましたが、意識していますか?
具体的な施策としてUX向上させる取り組みをおこなっていますか?
みんな、やっていない、いや正確にいえば「やれていない」と思います。
学習コストも手間も大きいですもんね
- スポンサーリンク
UX向上施策、やれない理由
顧客や使い手の「体験」へアプローチするってどういうことか、なるべく短くまとめると、
……まぁー小難しい!(イラっ)って感じなんですね。
で、実際になにやるかってなっても「定性リサーチ」とか「カスタマージャーニーマップ」とか、ペルソナ定義、ロールプレイとかとか、知らないよそんな単語ってのが並びだし……。
やれないよ!(ぽーい)
UXって言葉だけ知ってても、それ以上はようわからんし、勉強してるヒマも共有してるヒマもないし、結局、UXって言葉ごと一蹴する結末になります。
私もサイト運営を個人でおこなうなかでは、上にあげたようなちゃんとしたUX試作はまったく打てておりません。(よくて知り合いにちょっと使い心地を聞くくらい。)
でも、ユーザー体験はよくしてあげたい……そこで!!!
でも私だって善良な小市民のひとり、自分がサイト運営していたら「ユーザー体験はよくしてあげたい……」とは思うのです。
でもがっつり試作は打てない……。
……そう!
そこで!
そこで「ことわざ」、これですわ。
ことわざには「定型化された人間法則」が、みごとに再現されています!
ことわざにそってサービスのありかたを心がけるだけでもUX向上には効果的。
心がけるだけなら簡単だし
まぁことわざ利用、UX向上の意味的には当たらずしも遠からず、いや、当たっているような雰囲気の見当違いくらいなものですが、まぁ何かしら改善には役立つので、ちょっと言葉遊びのメモがてらご紹介します。
※お堅くいえばUX向上は、ユーザーがサービス・製品に触れる場面を時系列で可能な限り全て把握し、場面場面ごとの体験様相を把握、そしてユーザーの生涯においてサービス・製品がよりよく機能していくように、場面ごとの目標を定義して改善を回していくことです。だから「ことわざでサービス・製品のつくりを見直すっていうのは、UX向上施策ではなく、ただの自己満な改善のフリです」とかいわれたら、それはまぁ……おっしゃるとおりでございます!
UXをザックリと向上させるのに使える「日本のことわざ」
私がUXまわりを意識するときに、よく心がけている「ことわざ」をご紹介します!
終わりよければ、すべてよし
物事は最終の結末がもっとも大事であり、途中の過程は問題にならないということ。
途中経過で嫌な体験があっても、最後にハッピーだと全体評価は「ハッピー」と捉えてもらえます。
旅行とかわかりやすいですね。
途中、スタッフミスでチケットが手配されなかったり、事前情報とちがって観光地に入れなかったり、いろいろトラブルがあったとしても、旅行最終日に最高のディナーを食べてると「いろいろあったけど、いい旅行だったなぁ」って会話しちゃうものです。
たとえばブログ記事の読み終わりに「オチ」をつけるとか、ショッピングサイトなら購入完了時に、感謝メッセージをいれたり、おまけをサプライズしたり……
サービス体験の「完了時」にハッピーな工夫をすると、体験が向上します。
笑う門には福きたる
いつもにこやかに笑っている人の家には、自然に幸福がやって来るということ。
「笑い」には緊張を解いたり、不安感を和らげたり、関心を持続させたりする効果があります。
例えば……
- 長い説明・記事
- ミスしやすい手続き
- センシティブな交渉
- イラつきやすい待ち時間
などの体験は「笑い」によってユーザー体験がよくなるケースがあります。
だからどんなにお堅いサービスをやっていたとしても、たまにはおもむろに鼻毛抜いてみるとか、「笑い要素」をユーザー体験のなかに入れられないか、考えてみるといいです。
私は記事の文章が長くなりがちなので、すぐあいまにスベリ芸をいれる癖があります
いや、ほんとはドッカンいわせたいよ!?
一寸先は闇
これから先のことはどうなるのか、まったく予測できないことのたとえ。
これはちょっと設計よりの話。
とくにUI(画面の設計)まわりで、ついやってしまうことに「初見ユーザーから見えないので、一生、使われない」って事態があります。
1pxだって見えなきゃ、ユーザーには闇なのです
デザイナーさんって、情報を整理しはじめると、UIをスッキリ・スマートにしたくなる生き物です。
「タブUI」とか、「エキスパンドUI」、「ハンバーガーメニュー」とか、押せばでてくる画面を用意して、そこに色々、しまおうという話がでてきます。
でも
小さい頃から「知らない場所にはホイホイいっちゃダメよ!」といわれて育ち、人間は未知の領域って無意識に避けるようにできているので、折りたたんだ画面は、めちゃくちゃたまにしか使われなくなります。
よくある失敗は「お知らせ」を、ハンバーガーメニューのなかにいれるってやつ
こちらのお知らせしたいことが、ほぼすべてのユーザーに届かなくなります。
画面のスクロールですら、ほしい話の続きがあるとかじゃないと、スクロールされません
「見えない」っていうのは人の行動を止める、ものすごい力を持っているのです。
坊主憎けりゃ袈裟まで憎い
その人(物)を憎むあまり、それに関わるすべてのものが憎くなることのたとえ。
バッドUXで一度、憎まれると、関連するものも全部が憎まれます。
たとえば炎上した人がアンチの人の好きそうなサービスを運営しても、嫌いな人が作ったサービスなので使われません。
当たり前ですね
好かれたい人には絶対、嫌われるアプローチをしないのが鉄則。
そして嫌われている人、嫌われていい人には、そもそもアプローチしないのも大事。(ビジネス上の話です。)
袖すり合うも多生の縁
知らない人とたまたま道で袖が触れ合うようなちょっとしたことも、前世からの深い因縁であるということ。
これは営業上の話。
ベテラン営業さんとかに話を聞くと、こういう意見をくれますね。
こういうグレーもグレーでライトグレーな人々にも、なるべくよい体験を提供できるよう考えるのが、長いサービス・製品の運用には大切ってことですね。
身につまされます
百聞は一見にしかず
百回聞くよりも、たった一度でも自分の目で見たほうが確かだということ。
サイト運営では、ぜんぶ言葉で説明するより、画像で見せた方が100倍はやいってやつです。
手間だけど、画像化できるならする。
イラスト、写真、スライド、グラフなどなど。
利用しましょう。
これが大事です。
こんな文字だらけの記事で何言ってんだって感じですね……
悪い例です。すみません。
味を占める
一度味わったうまみや面白みを忘れられず、もう一度同じことを期待すること。
どんなに小さなことでも、成功体験を味わうと、それにむかって何度も行動を繰返すのが人間です。
サービスを利用してほしい場面では、その工程のなかに大小違わず「成功体験」をきちんとおりまぜてあげられるかが、大事になってきます。
たとえば会員登録とか、フォームを入力するごとに完了マークのアニメーションがでるだけで、楽しくなりますよね
成功体験というと盛大なものを想定しがちですが、それくらいの小さな体験でもけっこう変わってきます。
千里の道も一歩から
どんなに大きな事業でも、まず手近なところから着実に努力を重ねていけば成功するという教え。
どんなサービスでも、慎重に、丁寧に、ユーザーが一歩目を踏み出したくなる体験をデザインする必要があります。
逆にいえば一歩目がうまくいかなければサービスも成り立たないわけなので。
初手が大事ってことですね
キャンペーンをド派手にうっても、ダウンロードして、開いたらクソアプリって、あるあるですよね?(もっと酷いとローディングが長くて開かないとか。)
初手がダメな例です。
それだと、キャンペーン完了後に即削除されます。
サービス・製品の初見はめちゃめちゃ作り込んで、すばらしい体験を感じさせてあげましょう!
UXは難しくないことから始める
以上、350円のワイン片手に沖縄伊江島のケックンつまんで書いた記事でした。
うすしお味がおいしいよ
だから記事も半信半疑で読んでください。
UXって名前がかっこいいから「やってます」っていいたくなるんだけど、よくわからないですよね。
学習コスト高いし。
「まぁでもユーザーのために」って思って、よくわかんなくていいし、格好よくなくていいから、とりあえず簡単で役立ちそうなことから始めるのでも、UXのひとつの正解の道かなと思います。
ことわざの心がけでも、そこからユーザー体験が向上したらいいじゃないですか。
そしたら詳細にアプローチしたくなって、いつの間にか専門書読んだり、リサーチかけたり、予算割いてコンサル入れてカスタマージャーニーマップ作ったり、そういうことだってあるはずですからね。
UX向上、千里の道も一歩から
そういうことなんですよ、きっと!